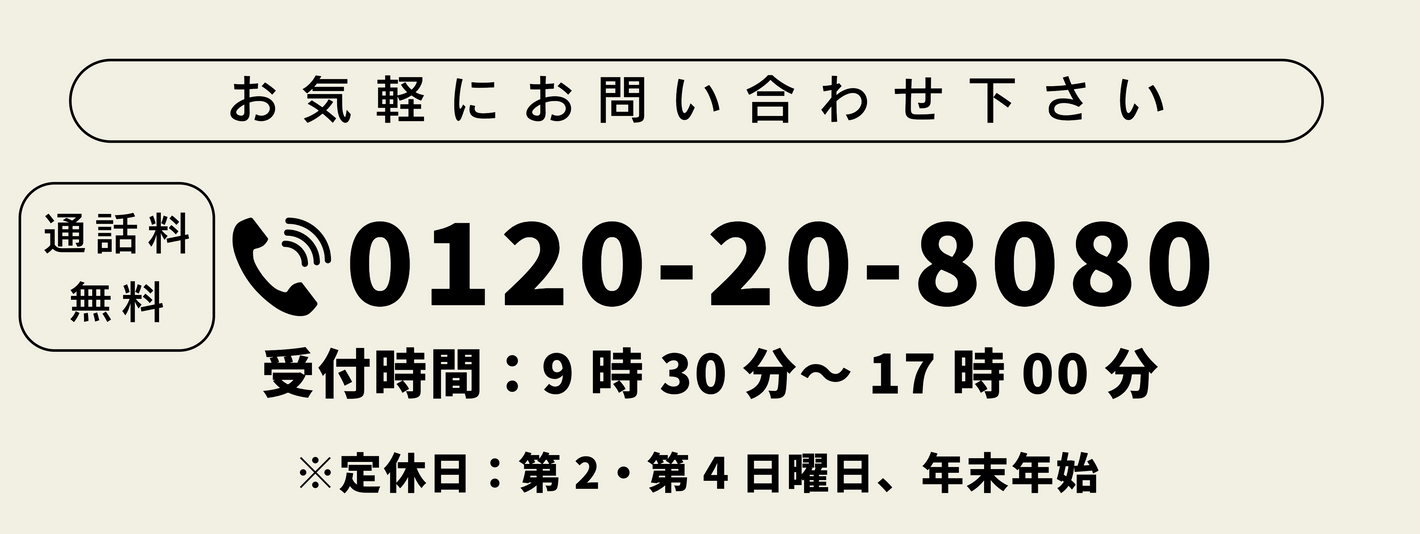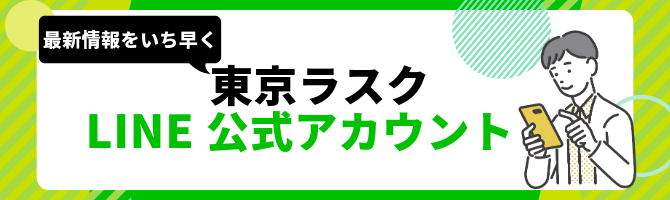皆さん、こんにちは!
いつも東京ラスクオンラインショップをご利用いただき、誠にありがとうございます。
東京ラスク社員であり大の映画好きな私 Haruが、「おやつのお供に観たい映画」をご紹介していくこのブログ。
映画について語りつつ、ラスクに合う楽しみ方もちょっと添えて。
ぜひ、ラスクとお気に入り映画で心ほどける時間をお過ごしください。
第9回では、イギリスの名匠ケン・ローチ監督による、福祉の網の目からこぼれ落ちる人々の現実を静かな怒りで描出した社会派ドラマを紹介します。
決して幸せな気分になる物語ではありませんが、現代社会が抱える問題を自分事としてとらえるきっかけをくれる、そんな力を持った作品です。
第69回カンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールを受賞した作品でもあります。
○わたしは、ダニエル・ブレイク(2016年製作)
スタッフ・キャスト
監督:ケン・ローチ
ダニエル役:デイヴ・ジョーンズ
ケイティ役:ヘイリー・スクワイアーズ
~あらすじ~
イングランド北東部にある町ニューカッスルに住む大工のダニエル・ブレイク。59歳の彼は心臓に病が見つかり、医師からは仕事を止められてしまう。しかも複雑な制度に翻弄され、国の援助を受けられない。そんな中、二人の子供を抱えるシングルマザーのケイティを助けるダニエル。それをきっかけに彼女たちと交流し、貧しくとも助け合い絆を深めていくが、厳しい現実を前に次第に追い詰められていく。
引用:MOVIE WALKER PRESS(https://press.moviewalker.jp/mv61684/)
◆見どころポイント◆
①社会保障制度の矛盾と「制度の暴力」
本作の柱となるのは、公的支援制度の冷酷さと矛盾です。
主人公は医師から「働けない」と診断されていながら、行政上の基準では「働くことができる」と機械的に処理されてしまいます。
また、申請過程はインターネットと大量の書類手続きが必須。高齢でパソコンの使い方がわからないダニエルや、生活に余裕のないケイティにとって、この「デジタル化」は福祉の門戸を閉ざすものとなっています。
制度そのものが弱者を選別し排除する仕組みとなっている点は非常にリアルであり、日本でも実際に起こっていることです。
役所の担当者は「決まりですから」「オンライン申請で」と繰り返しますが、ここに“人間としての対話”はありません。困窮者を助けるはずの公的サービスが、規則のもとに人間味を喪失し、サービス利用者に“制度の暴力”として降りかかる構図が全編を覆います。
給付判定のロジック、人間的配慮を切り捨てたマニュアル主義による悲劇ー作品はそれらを特別な物語ではなく、「現代のどこにでもある構造的な過ち」として突きつけます。
こうした制度的暴力が、個々人の人生にどれだけ深く傷を残していくのか。ダニエルの絶望やケイティの飢えを通して、観客は自分ごととして突き付けられます。
②人間の尊厳と他者への思いやり
本作のもう一つの主軸となるのは、尊厳を守ろうとする人間の姿、そして弱者同士の連帯です。
援助を求めて役所に通うダニエル、子ども達を抱えながら食料に困窮するケイティー彼らの抱える苦しみは、「自己責任論」では到底説明がつきません。
ただし、映画は「可哀想な人々」を描くだけにはとどまりません。
ダニエルは自分の苦境の中でもケイティ親子や隣人たちに手を差し伸べ、小さな善意を積み重ねます。貧しさや孤独のなかにあっても絶対に失われない、“人としての誇りとやさしさ”。ダニエルがケイティの家を修理したり、ケイティが子どもたちを守ろうとする姿は、助け合いが精神的な救いとなることを強く示唆しています。
食料品の無料配布所(フードバンク)でケイティが空腹に耐えきれなくなる場面では、貧困がどれほど「人間性を試す瞬間」を作り出すのかが痛烈に描写されます。窮状に置かれていても、恥と誇り、他者を思いやる心を選択し続ける二人の姿は、決して特別な英雄譚ではなく、誰もが持つ「人間らしさ」の本質を浮き彫りにします。
役所や制度の冷淡さに対抗できるのは、公式な支援でも一時的な施しでもなく、「目の前の人間への誠実な向き合い」だけだという救い。ケン・ローチ監督らしい、連帯の信念と“人間への信頼”の物語がここに貫かれています。
③ ケン・ローチ監督の演出とキャスト陣の素晴らしい演技
本作で感じられるリアリズムは、ケン・ローチ監督の最大の特色です。
ドキュメンタリーに近い質感と、即興性を意識した演出、生活感まで正確に再現されたロケーションや空間描写によって、観客は映像の「作り物」感から切り離され、まるで物語の当事者であるかのような感覚を味わいます。
また、ダニエル役のデイヴ・ジョーンズや、ケイティ役のヘイリー・スクワイアーズら主要キャストの表情やしぐさ、さらには名もなき通行人や窓口職員まで、その演技はまったく「演じている」印象を与えません。
生活の場そのものを切り取ったような存在感が、言葉に頼らない説得力を映画にもたらしています。
ケン・ローチ監督はストーリー展開やカメラワークにも過度な演出を一切加えません。BGMはほとんどなく、画面にあるのは自然光や生活音が中心。
それがダニエルたちの日々の辛さや希望の無さを、大げさではなくじわじわと染みこむ現実感として観客に伝えます。
特筆すべきは、作品全体を覆う「静かな怒り」のトーンです。誰かを糾弾するでもなく、号泣や雄弁な演説に頼るでもない。
ただしラストにかけて投げかけられる、ダニエルが自らの尊厳とともに残す力強い言葉。その瞬間、物語は観客の心に深く沈殿します。
ケン・ローチ監督による社会に対する誠実で切実な視線、それを覆い隠さぬ淡々としたカメラのまなざしー本作の“リアルさ”は、観る人の現実認識を更新し、社会の問題を「自分の隣の問題」と強く自覚させます。
まとめ
『わたしは、ダニエル・ブレイク』は、福祉先進国イギリスの光と影、そのシステムの網目の隙間に落ちる一人ひとりの物語を細部に至るまで丁寧に描き尽くしています。
制度の闇と、それでも失われない人間性の光ーこの映画が観客に投げかけるものは、希望か絶望か。
現代社会において“生きる”とは何か。誰もが等しく答えを探さずにはいられない、誠実かつ切実な一作です。
それでは、映画とともに 素敵なラスク時間を