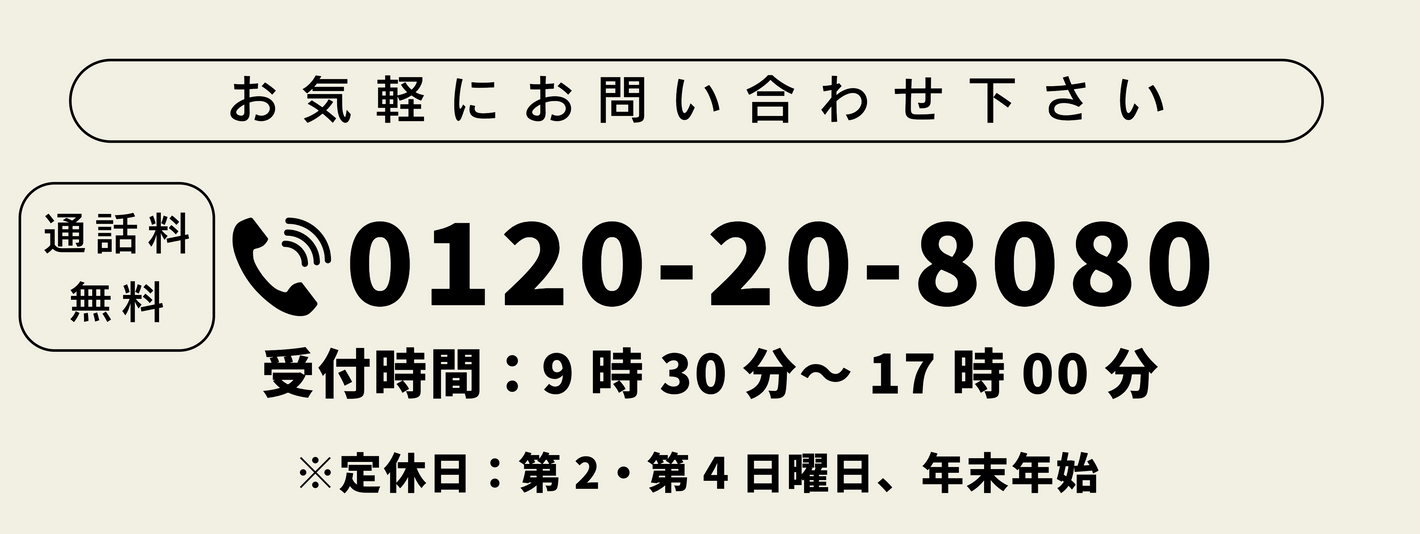皆さん、こんにちは!
いつも東京ラスクオンラインショップをご利用いただき、誠にありがとうございます。
東京ラスク社員であり大の映画好きな私 Haruが、「おやつのお供に観たい映画」をご紹介していくこのブログ。
映画について語りつつ、ラスクに合う楽しみ方もちょっと添えて。
ぜひ、ラスクとお気に入り映画で心ほどける時間をお過ごしください。
第34回では、ニュージーランドの都市の片隅で、母としての尊厳と「正義」を取り戻そうと走り続ける女性の奮闘を描く、切実で骨太なヒューマンドラマを紹介します。
胸が痛くなるほど切ない物語ではありますが、主人公の魅力的なキャラクターによって、明るさと希望が全編を包む傑作となっています。
○ドライビング・バニー(2021年製作)
スタッフ・キャスト
監督:ゲイソン・サヴァット
バニー役:エシー・デイヴィス
トーニャ役:トーマシン・マッケンジー
~あらすじ~
バニーはとある事情で娘と離れて妹夫婦の家で暮らしている。愛する娘とは監視付きの面会交流でしか会うことができないが、それでも娘との生活を再開させることを夢見て必死に働いていた。ある日、妹の新しい夫であるビーバンが姪のトーニャに言い寄る場面を目撃したバニーは、ビーバンに立ち向かうも家を追い出されてしまう。家を失ったバニーは、救い出したトーニャと共に娘を奪い返す作戦を立てる。
引用:MOVIE WALKER PRESS(https://press.moviewalker.jp/mv78108/)
◆見どころポイント◆
①“普通”を手に入れる難しさー経済的弱者のリアルをまっすぐに
バニーが追い求めるのは豪奢でも英雄的な勝利でもなく、「子どもの誕生日にケーキを用意して一緒に祝う」といった、誰の家にもあるはずの“普通”。そこへ至るまでの壁が、あまりに多く、あまりに高いことを映画は痛いほどリアルに見せます。
仕事と住居の不安定さ、福祉制度の冷たい仕様、保証金や書類のハードル、信頼の欠片すら持たない相手に頭を下げる屈辱。信号待ちの車のフロントガラスを拭く小銭稼ぎという反復が、前に進みたいのに押し返される日々のメタファーとして効いています。
継父を本能的に拒むトーニャが、母の愛を疑いながらもバニーに寄り添う姿は、傷ついた者同士が支え合う微妙な均衡を映し出し、観客の胸を掴みます。
中盤、彼女を一時的に受け入れる一家の温もりが差し込む場面は、移民という立場から弱者に寄り添う視線が滲むようにも感じられ、社会の周縁が互いに手を取り合う希望のスケッチとして心に残ります。
過剰な説明を避けた演出により、シビアで現実的な積み重ねが静かに効いてくる—その手触りが、この作品の切実さと説得力です。
②タイトルが射抜くテーマー“正義”と“尊厳”の間で選び続ける
原題の“The Justice of Bunny King”は、法的に定義された正しさと、当事者が身を賭して守ろうとする正しさのズレを正面から問います。
故殺の前科という烙印、制度の網目、偏見と無理解。バニーの選択は規範から外れて見えることがある一方で、別の選択肢が現実的に閉ざされた状況での“ほとんど唯一の手段”として切迫しています。
映画はジャッジを急ぎません。むしろ、観客に自分の物差しを問い直させる。
どこからが“行き過ぎ”で、どこまでが“尊厳を守るために必要な抵抗”なのか。重くてやりきれない出来事が続いても、そこかしこに茶目っ気と人間らしいユーモアが差し込み、バニーの尊厳は決して折れない。
終盤に向けても切なさは濃く残りますが、その奥の奥で確かな希望の火が消えないことを感じさせてくれます。
観終わってからも、私たちは日常の中で何を“正義”と呼ぶのか、他者の痛みにどう手を伸ばすのかを、しつこく考え続けるはずです。
だからこそ、この物語は単なる社会派ドラマを越え、観客の生き方に反射する鏡となります。
③エシー・デイヴィスの圧倒的体温ー“普通”を渇望する母の息づかい
本作の心臓は、主人公バニーの呼吸と鼓動そのものです。
彼女は決して模範的なヒロインではありません。短気で、計画性に欠け、時に危うい賭けにも出る。しかし、すべての衝動の核にあるのは「子どもを守りたい」という揺るがぬ愛。
バニーを演じたエシー・デイヴィスは、汗ばんだ手の震え、噛み締めた歯の隙間から漏れる息、追い詰められた瞬間にふと覗く茶目っ気まで、生活者の体温を寸分違わずスクリーンに刻みます。
ホラー映画『ババドック 暗闇の魔物』での表現力とはまた違った、素晴らしい演技を見せてくれています。
姪トーニャの繊細さと反骨心がバニーの暴発と響き合い、二人の間に生まれるごく小さなユーモアやアイ・コンタクトが、過酷な現実に人間らしい光を差し込みます。
「思っていたより重くて切ない」のに、彼女は最後の最後までユーモアと強さを忘れない。その人間臭さが、この物語を“観客自身の隣にある現実”として立ち上げ、観る動機を強くしてくれます。
まとめ
『ドライビング・バニー』は、経済的弱者が“普通”を求める旅の切なさと、母としての尊厳を死守しようとする強さを、ニュージーランドの都市のリアリズムの中に刻み込んだ秀作です。
茶目っ気と痛みが同居する語り口は、やりきれない余韻を残しつつ、その奥で消えない希望を確かに感じさせます。
観ればきっと、あなた自身の“正義”について語りたくなるはずです。
それでは、映画とともに 素敵なラスク時間を