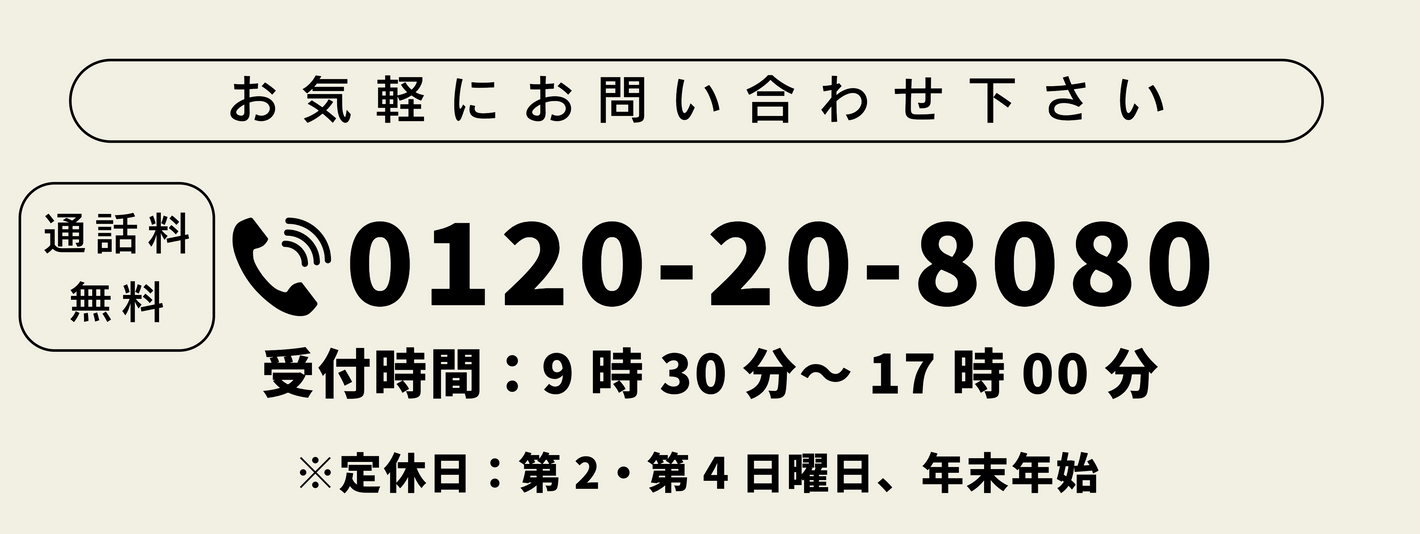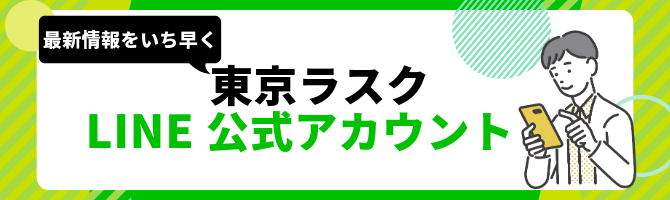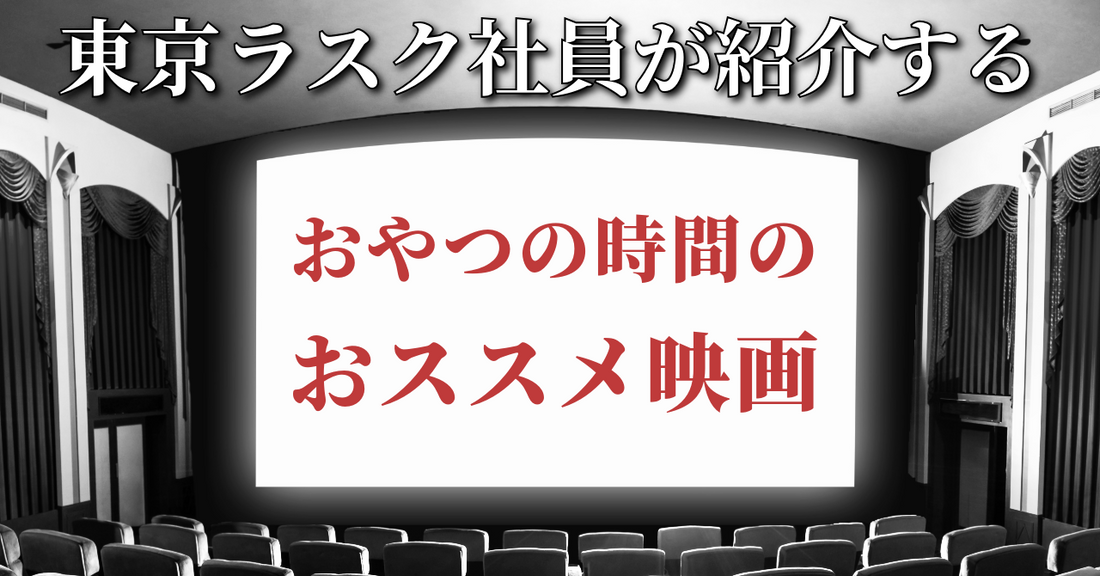皆さん、こんにちは!
いつも東京ラスクオンラインショップをご利用いただき、誠にありがとうございます。
東京ラスク社員であり大の映画好きな私 Haruが、「おやつのお供に観たい映画」をご紹介していくこのブログ。
映画について語りつつ、ラスクに合う楽しみ方もちょっと添えて。
ぜひ、ラスクとお気に入り映画で心ほどける時間をお過ごしください。
第18回では、人間が姿を消した世界で動物たちが生きるさまを描いたアニメーション映画を紹介します。
哲学的な問いと現代的な寓話性、そして圧倒的な映像美が融合し、生命の流れや共生の本質に迫った作品です。
第97回アカデミー賞長編アニメーション賞を、『インサイド・ヘッド2』や『野生の島のロズ』などビッグタイトルを抑えて受賞しています。
○Flow(2024年製作)
スタッフ・キャスト
監督:ギンツ・ジルバロディス
~あらすじ~
猫の主人公は、もう人間の姿がどこにもない世界で目を覚まします。突然の変化に戸惑いながらも、やがて犬や鳥、他のさまざまな動物たちと出会い、洪水などの自然災害に巻き込まれながら共同体を築いていきます。先行きの見えない“流れ”の中、彼らは本能的な恐れや葛藤、大切なものへの執着を持ちながらも、それぞれの思いを胸に見えない未来へと進む旅に導かれていきます。
◆見どころポイント◆
①森の光と水の流れが生み出す圧倒的なアニメーション表現
『Flow』の第一の見どころは、アニメーションならではの圧倒的な映像体験です。
本作は、自然界に存在する繊細な現象を驚くほど精細に描写しています。例えば、森の木漏れ日のゆらぎや水面に差し込む光、霧が立ち昇る川の岸辺、雨が葉を伝い流れる様、そして洪水によってすべてが飲み込まれていくダイナミックな動きーこれらが、水彩画に近い独特のタッチと柔らかい色彩で表現され、作中の「流れ=Flow」という主題を五感で感じ取れるようになっています。
アニメーションの中でさりげなく描かれる自然の音や光、影の変化は、環境の呼吸や時の流れさえも実在感を持って表しています。この表現は単なる写実を超えて夢と現実の間に観客を誘い、物語世界そのものへ没入させます。
また、主人公である猫や他の動物たちの仕草や身体表現にも徹底したこだわりがあります。猫がおそるおそる歩く姿、耳やしっぽの振る舞い、犬たちが群れを成しながらもどこか臆病な一面を覗かせる表情、鳥たちが羽を震わせる瞬間など、繊細でリアルな動きがチャーミングかつ魅力的に描かれています。
これらは決して擬人化されたものではなく、あくまで動物本来の持つ動きがベースになっており、そのリアリティが観客に「異質な生」を感じさせると同時に、その中に自分たち人間と重なる何かを直感的に認識させます。
さらに、音響や音楽も本作のビジュアル体験と切り離せません。台詞や説明がほとんどない分、さまざまな環境音や動物の鳴き声、川のせせらぎなどが繊細に配置されています。それにより、観客は物語を理解するのではなく、あたかもその場の空気や流れを感じながら「体験」することができるのです。
『Flow』の映像と言葉にならない感覚が一体となり、日常では得難い感受性に直接訴えかけてきます。
②共生の現実と現代社会への鋭い投影
二つ目の見どころは、「共生」というテーマの深さとその現実的な描写です。
『Flow』に登場する動物たちは、命の危機に晒され自分の居場所や大切なものを失いながら、必ずしも自ら選んだのではない“共同体”の中で互いに助け合い、多様な価値観の中で生きることを強いられます。
作中では、猫が犬たちに追われ恐怖し、最初は新しい共同体に溶け込むことができなかったり、洪水によって動物たち全員がそれぞれの居場所を見失っていく過程がリアリスティックに描写されます。こうしたシーンは、「難民」として自分の故郷を追われる人々や、異文化・多民族社会に生きる現代の私たちの姿を強く想起させます。
この集団の中では、理解し合えない痛みやすれ違いも避けがたいものとして描かれます。大切なものを失い傷つきながらも、動物たちはどうにか共存し、新たな道を模索していきます。共生とは単に仲良く助け合うことで完結するものではなく、それぞれが譲れないものや価値観と折り合いをつけながら試行錯誤する過程の連続であり、そこには痛みや犠牲が必ず伴うという現実的な姿勢が、『Flow』の核として鮮明に描かれています。
特に印象的なのは、ヘビクイワシのエピソードです。猫に寄り添い、違う存在を理解しようとする唯一の存在でありながら、その姿は周囲の同調圧力や集団による排除・攻撃によって傷ついていきます。
少数派や異質な考え方を持つ「理解者」が時に集団から疎外される社会の構造、そしてその孤独と痛みを物語の中で象徴的に浮き彫りにしています。この描写は非常に現代的で、観客自身の体験や現実社会と無意識のうちに重ねあわせてしまう力を持っています。
『Flow』は、そのすべてを決して美しい共生の理想像だけでまとめません。協力し合いながらも、必ず強い摩擦や自己喪失を経験する「生の現実」。その複雑さを静かに、しかし逃げずに、描いています。
③動物で描く“人間”ー普遍性と寓話性の融合
最後の見どころは、擬人化せずに動物たちの視点を維持したまま、徹底して人間社会の物語として投影できる本作の「寓話性」と「普遍性」です。
猫や犬、鳥は人間の言葉を話しませんが、その知性や感情、葛藤の深さは明らかに私たち人間にも響くものになっています。これは動物固有の本能や群れの行動からだけでなく、個体同士の間に生まれる相互不理解や、お互いを思いやったり妬んだりする複雑な心理に、作り手が徹底的に寄り添っているからです。
この作品では、「今、ここにあるという感覚」ー過去でも未来でもなく、不安定な流れの中にある“いま”を生きることが強調されます。流れに抗うのではなく、それとともに流されることを受け入れる猫の姿は、まるで現代社会を生きる私たちが直面している不確実な時代や価値観の揺らぎと重なります。
猫は、自分が思い描いた理想通りにはいかない現実を受け容れ、他者と関わり合うことの不可避性、そして一人では生きられない事実に向き合います。
動物たちは決して人間のようにデフォルメされてはいませんが、その行動や苦悩、選択には、社会の中で生きる「個」としての悩みや希望が投影されています。観客は物語世界に距離を保ちながらも、自身の生き方や社会とのかかわり、不理解や孤独への向き合い方について深く考えさせられるのです。
この「他者とともに生きるということ」「痛みや喪失も抱えながら前に進むしかないという認識」「異質なものを理解しようとすることの困難さ」など、動物たちの生を通して語られるテーマは、あらゆる時代・社会・文化を超えて人間に普遍的な問いを投げかけます。だからこそ、『Flow』は台詞や説明を排した五感への訴求によって、鑑賞者ごとに異なる余韻や解釈を残しうる作品といえるでしょう。
まとめ
『Flow』は、圧倒的な自然描写と直感的・身体的な感覚を呼び覚ますアニメーションによって、共生の理想とその現実的な困難を描き、動物たちの姿を通して現代社会を映し出す映画です。
優しさと痛み、希望と絶望がないまぜになった流れのなかで生きることの本質に、説明や答えではなく、体験と余韻で深く切り込んできます。あらゆる世代や境遇の鑑賞者に、生きることと他者とともにあることの意味を静かに問いかけ、鑑賞後も長く心に残り続ける作品となっています。
それでは、映画とともに 素敵なラスク時間を